
白山 弘経寺
さて、
新四国相馬霊場八十八ヶ所と周辺スポットポタリング。
今回は、
取手市白山地区から弘経寺82番を訪れる。

大鹿山 清浄院 弘経寺は、
応永二十一年(1414年)に嘆誉良肇上人により開創された。
飯沼と結城の各弘経寺と共に、
関東の三弘経寺の一つとされる。
境内に入ると、
参道北側に六地蔵。

この六地蔵は、
寛文五年(1665年)のもの。

札所塔は、
文政二年(1819年)のもの。

右下にある道標は、
年紀不明。

、
こちらも、
道標。

この道標は、
大正元年(1911年)のもの。

参道を行くと、
正面には山門。

大鹿山、
とある扁額。

鐘楼門で、
上には鐘があるがもちろん上れない。

山門を抜けて左手には、
左から不明の石祠に水の文字があるので水神宮だろう。
そして、
不動明王と読める石祠。

こちらは、
英霊観堂。

終戦までは観音堂として本尊に観音菩薩立像を祀ってあったが、
戦後町内の将兵の位牌を堂内に掲げて御霊を祀っているようだ。

山門を抜けて、
右手を行く。

奥には、
白山神社。

白山幼稚園があって、
門の前はこんな感じ。

他には、
仏教詩人である坂村真民さんの七節からなる詩の三節を自筆で書かれた歌碑。

そして、
山門を抜けた正面には本堂。

三度の火災に見舞われ、
現在のものは昭和四十七年(1972年)のもの。

右隣にあるのは、
客殿。

本堂の左手前には、
勢至丸像。
勢至丸は、
浄土宗祖法然上人の幼名。

その近くには、
明治二十一年(1888年)の供養塔。

左手前に見えるのは、
道標。

そして、
82番の札所塔。

これは、
安永五年(1776年)のもの。

82番

その先に、
82番の大師堂。

中は、
こんな感じ。

手前の手水鉢は、
安政三年(1856年)のもの。

その先にも、
もう1つお堂がある、

中は、
こんな感じ。

というわけで…
今回の新四国相馬霊場八十八ヶ所と周辺スポットポタリングは、
取手市白井地区から。
新四国相馬霊場札所、
白山 弘経寺 82番を訪ねた。
石造物は、
そんなにない。


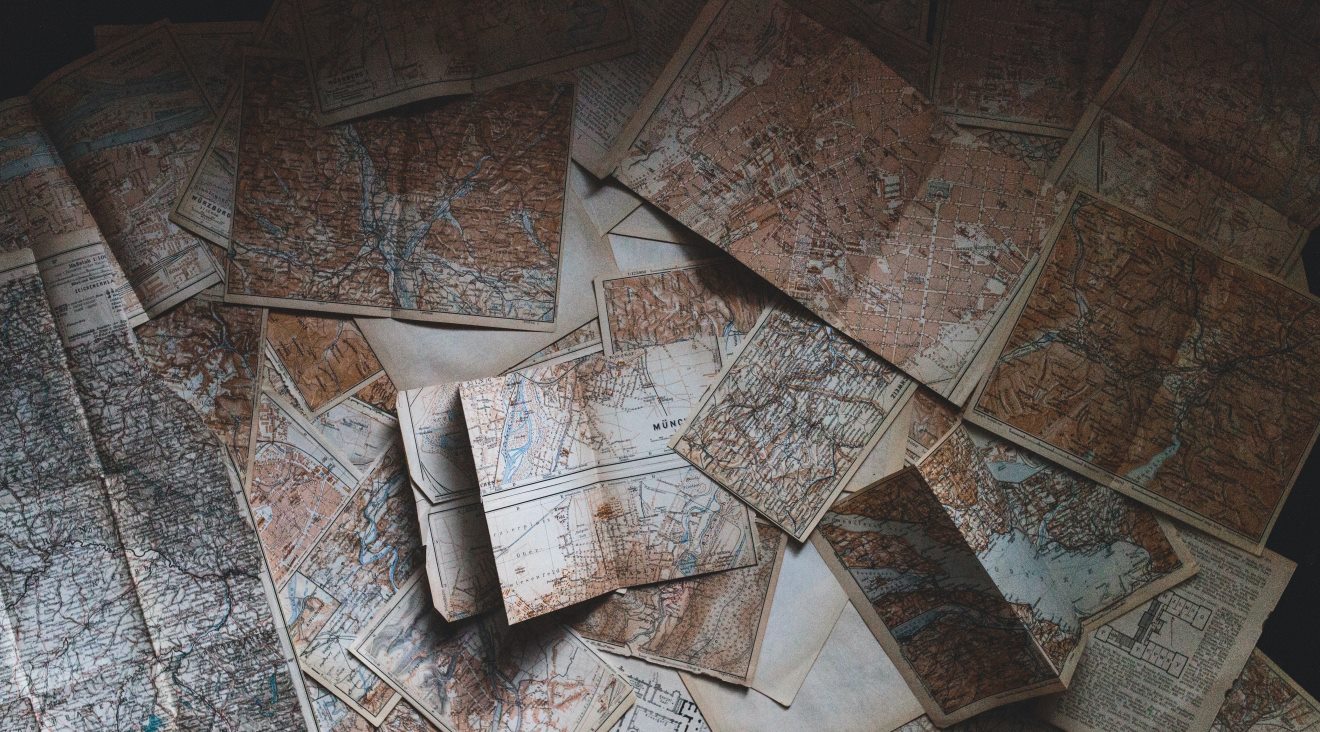



コメント