
布施地区 圓性寺
今回の新四国相馬霊場八十八ヶ所と周辺スポットポタリングは、
柏市布施地区から。
布施地区に4つある札所の1つ、
布施 圓性寺 85番。
概要

飛龍山 圓性寺、
創建年代等は不詳。

ただ江戸時代には西円寺(現西栄寺)の門徒寺で、
香取・妙見・山王・天神の各神社の別当を勤めていたという。

本尊は、
不動明王。
宝篋印塔周辺の石造物
ここには、
結構いろいろと石造物がある。
宝暦二年(1752年)、
宝篋印塔がある。



傍には、
多分寛政二年(1790年)の手水鉢。

新四國大師道道標と、
多分新四國八十五番札所塔。

境内左手の石造物
境内左手には、
いろいろと並んでいる。

一列目左から、
文政十三年(1830年)文字青面金剛塔。

基礎台には、
三猿。

享保四年(1719年)、
青面金剛塔。

青面金剛は、
六臂数珠持ち。

両脇には、
二童子。

三猿も、
ちゃんといる。

文化十三年(1816年)、
文字青面金剛塔。

明治十九年(1886年)、
弘法大師一千五十年遠忌塔。

二列目左から正徳五年(1715年)光明真言持斎供養とある地蔵塔、
文化三年(1806年)文字青面金剛塔。

文化元年(1804年)自然石型文字青面金剛塔、
不明の石仏。

三列目左から、
宝暦五年(1755年)三猿庚申塔。

倒れてしまっているが、
そのままになっている。

年紀不明、
文字庚申塔。

三猿は、
こんな感じ。

元禄八年(1696年)、
三猿庚申塔。

三猿は、
こんな感じ。

宝暦四年(1754年)、
三猿庚申塔。

三猿は、
こんな感じ。

少し離れて、
年紀不明普門品拾萬巻供養碑。

享保四年(1719年)、
護讃地蔵。

年紀不明、
善光寺参拝記念碑。

大師堂裏の石造物
右奥に見えるのは、
こんな感じ。
一列目左2基は不明、
右端は明治二十四年(1891年)延命地蔵。
二列目は左から相州八ヶ所観世音参拝記念碑、
明治二十四年(1891年)二十三夜塔。
更に明治十年(1877年)ヨリ始明治二十九年(1891年)申年十二月建立と側面にある、
鳥猟繁栄供養塔。

そして、
倒れて2つに分かれてしまっている明治二十九年(1891年)三日月不動尊。

本堂左手奥の石造物
本堂左手奥にを進むと、
木の根元には不明の石祠。

手前は、
弘法大師一千百年御忌記念碑かな。
更に手前には、
馬頭観世音塔が並ぶ。

天明二年(1782年)のものや、
寛政十一年(1799年)のものなどいろいろ。

ただ、
どれも文字塔なのだ。

馬頭観世音塔群の奥の小高いところに、
木祠がある。

堂内には、
天保三年(1832年)の石像。

聖観音みたいだけど何の像か?はちょっとわからないが、
八手でいろいろ持っている。

基礎台には、
土谷年寄中とあるのかな。

この一角の右手の小高い場所には、
やはり木祠がある。

上っていくと、
鈴には三峯山の木札。

その奥には、
妙見堂の扁額。

中を覗かせて頂くと、
こんな感じでよくわからない状態。

そして、
先には六地蔵。

85番

さて、
この圓性寺は新四国相馬霊場八十八ヶ所85番札所である。


彫刻は、
それほど凝ったものではない。

お堂の扉は開かれており、
中には弘法大師坐像が見える。

近付くと、
こんな感じ。

御詠歌額は掛かってなかったが、
堂内にあった。

大師堂前には、
新四國八拾五番の札所塔。

というわけで…
今回の新四国相馬霊場八十八ヶ所と周辺スポットポタリングは、
柏市布施地区から。
布施地区に4つある札所の1つ、
布施 飛龍山 圓性寺 85番。
ここは札所というだけではなくて、
思ったよりも石造物が多くてかなり見応えがあるところとなっている。


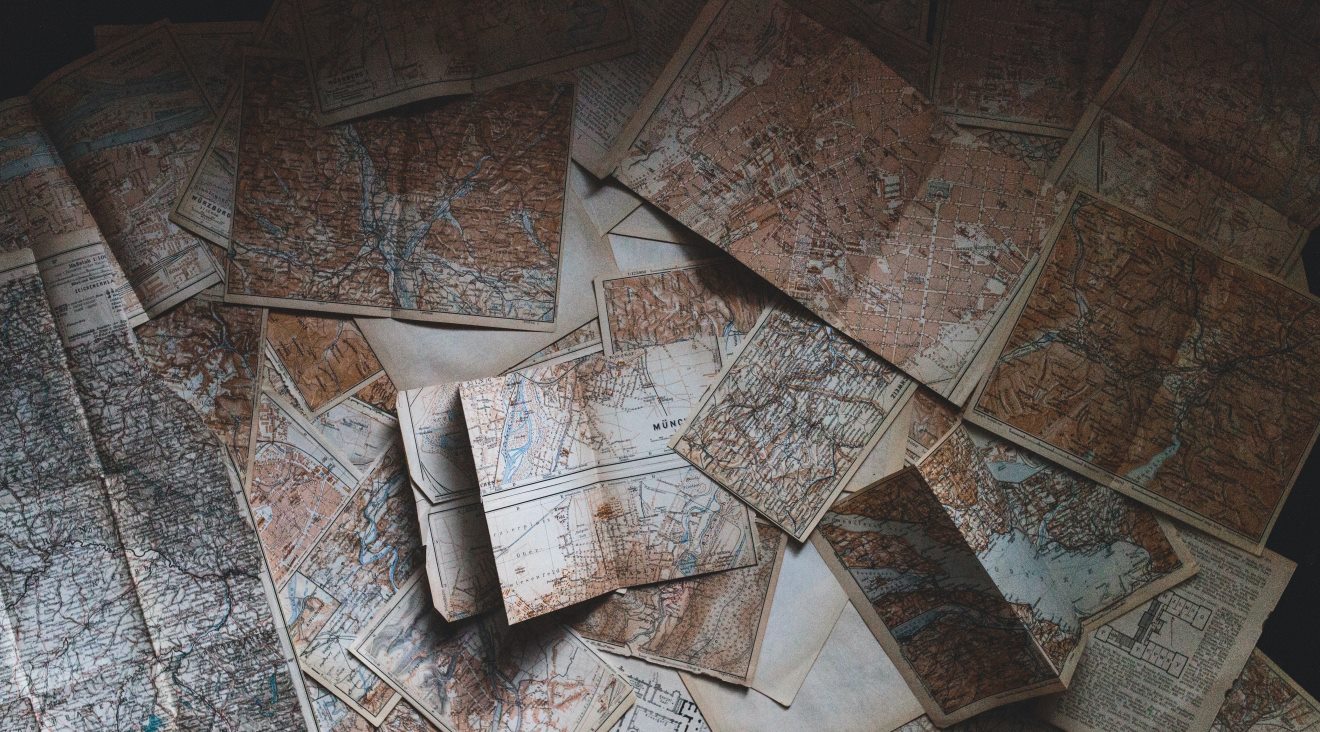



コメント