
取手市新町 石引墓地入口の庚申塔群
さて、
新四国相馬霊場八十八ヶ所と周辺スポットポタリング。
今回は取手市新町地区から、
周辺スポットということで石引墓地入口の庚申塔群。
石引墓地は、
前回の愛宕神社のR6を挟んだ向かいの高台にある。
その入口右手の一角に沢山の庚申塔が4列、
かなり狭い間隔で並んでいる。
1列目

1列目に見えるのは、
文化六年(1809年)の六地蔵。
2列目
2列目の左端2基は、
写真に撮らなかった不明石造物。
ただ2基目側面には、
安政四年(1857年)・文久三年(1863年)・天保十四年(1843年)と刻まれていた。

その隣は、
元文三年(1738年)二十三夜塔。
元文三戊午天 本町/奉供養廿三夜石塔/九月 同行拾二人、
とある。
石塔って刻まれているのは、
初めて見た表現かもしれない

その右は、
宝永五年(1708年)二十三夜塔。
奉造立廿三夜待供養祈所、
宝永五戊子天九月廿三日 施主とある。

宝永四年(1707年)、
二十三夜塔。
1番右端に多分お寺の名が刻まれているみたいだけど、
別當〇〇寺しかわからない。
あとは、
奉供養廿三夜待為安樂/宝永四丁亥天九月吉日/大鹿村同行八人とある。

正徳五年(1715年)、
二十三夜塔。
正徳五乙未歳/奉造立十十三夜待供養為二世安樂也/九月吉祥日/西照寺?、
とある。

享保四年(1719年)、
庚申塔。
享保四己亥天十月吉日/同行弐拾四人/奉造立庚申待供養為二世安樂之、
とある。

下には、
ハッキリとした三猿。

正徳三年(1713年)、
庚申塔。
テ時正徳三癸巳天九月吉日/奉造立庚申供養祈所/同行十人、
とある。
ここにも別當〇勝寺とあるので、
これまで何回か出てきたのは廃寺となっている最勝寺もしくは西照寺と書かれているんだろう。
写真右下は、
享保四年(1719年)の二十三夜塔。

こちらの三猿も、
かなりクッキリ。

3列目
3列目左からは、
元文三年(1738年)二十三夜塔。

年紀不明観音像、
宝永七年(1710年)二十三夜塔。

寛政四年(1792年)、
勢至菩薩。

正徳元年(1711年)、
巳待塔。
隣の小さいものは、
昭和三十九年(1964年)弁財天。

元禄二年(1689年)と宝永五年(1708年)、
二十三夜塔。

4列目
4列目左から、
享保十年(1725年)庚申塔。

二鶏と、
三猿。

正徳三年(1713年)、
青面金剛塔。

言わ猿と聞か猿の顔が平らになっているのが、
妙に面白い。

天和二年(1682年)、
庚申塔。

三猿は、
良く残っている。

元禄十三年(1700年)、
青面金剛塔。

久々な気がする、
ショケラ持ち。

三猿も、
ちゃんと残っている。

元禄七年(1694年)、
庚申塔。

これも三猿が目までぱっちり、
随分きれいに残っている。

元禄十三年(1700年)、
青面金剛塔。

お顔は少しわからなくなっているのが、
残念。

2つに割れてしまっているのが、
正徳五年(1715年)青面金剛塔。

元禄十年(1697年)、
二十三夜塔。
奉待のあとの文字は何と読むんだろう?
月輪とあるのも珍しい。

ここでやっと、
別當最勝寺とちゃんと読めるものがあった。

元文五年(1740年)、
青面金剛塔。

下には二鶏と、
三猿。

というわけで…
今回の新四国相馬霊場八十八ヶ所と周辺スポットポタリングは、
取手市新町地区から。
大利根橋を渡ったR6の脇の高台にある、
新四国相馬霊場札所第87番愛宕神社の向かいの高台にある石引墓地入口の庚申塔群。
天和二年(1682年)に始まって元禄時代のものなども結構あって、
かなりの充実ぶり。
もう少し間隔空けて並んでいると、
もっと良いんだけれどなあ。


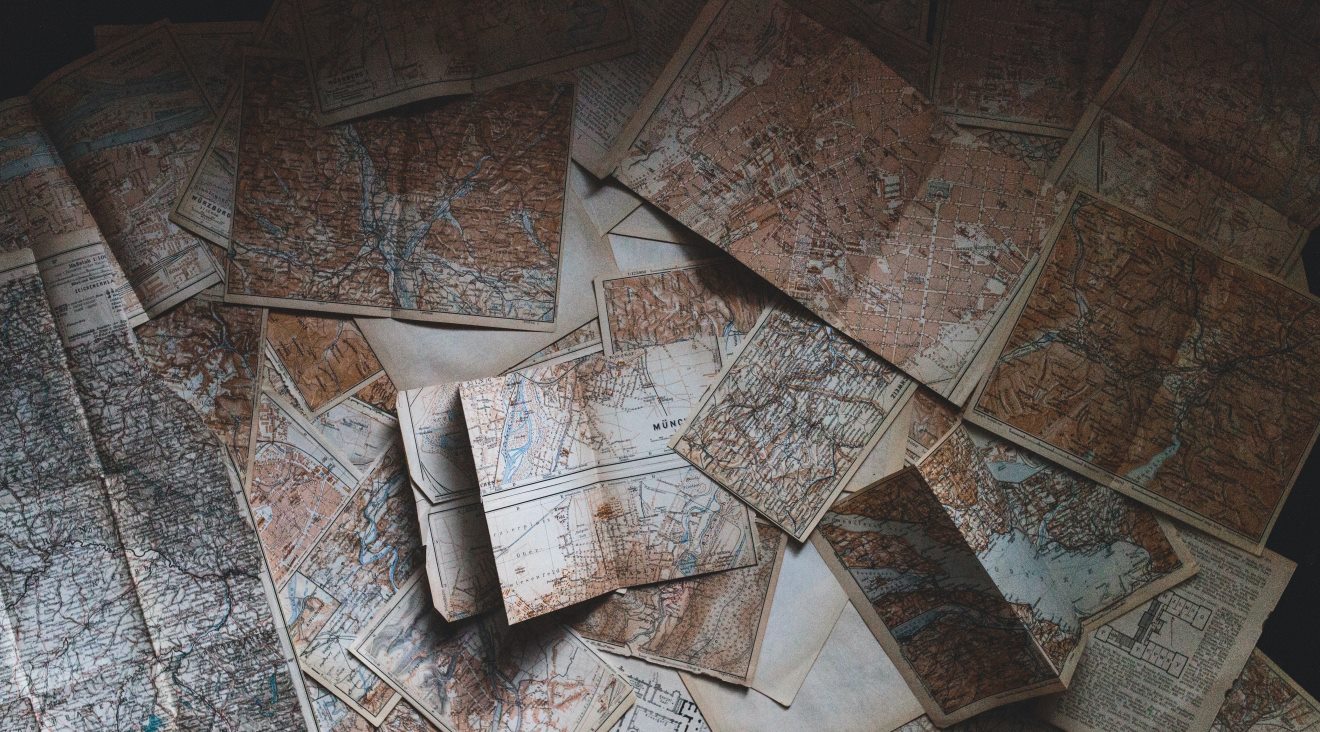



コメント