
岡発戸 待道社
今回の新四国相馬霊場八十八ヶ所と周辺スポットポタリングは、
我孫子市岡発戸地区から。

その敷地内にあるのが、
待道社だ。
待道講とは?
待道講は以前にも出てきてたことがあるけど、
利根川流域の下総地域に見られる安産祈願の女人講。
ちなみに、
まつどっこうと読むみたい。
お腹が大きくなってる妻と、
その旦那様がある日待合わせをした。
しかしながらなぜかお互いに別々の場所で相手を待っていたため、
その女性は待っている間に産気づいてしまう。
そして、
道の端にムシロを敷きそこで赤子を産んで死んでしまった。
というような、
話がある。
それで道で待つということから、
待道と言われるようになったらしい。
ここが信仰発祥の地

この待道社の玉垣の柱に安永4歳末12月吉日とあり、
なんとここが信仰発祥の地とされているのだ。
まあ確かに信仰にも発祥の地があって然りだけど、
ここにあるとは知らなかった。

八幡神社の狛犬の左脇に、
小さいながら鳥居がある。
その柱には、
天保十一年(1840年)/當村女人講中と刻まれている。


小ぶりの燈篭は、
文政十三年(1830年)のもの。


石祠は、
やはり玉垣に囲まれている。
白泉寺には、
待道講の版木が伝わるらしい。
横約26cm・縦約68.5cm・厚さ約3cmの板で赤児を抱いた観音菩薩像と共に、
日本最初・女人守護・安産待道大権現・三月七月九月当ル十七日・下総国相馬郡岡発戸邑・別当白泉寺と彫られているようだ。
この版木から刷りだされた紙片(附)は軸装されて待道講の会場中央に掲げられたほか、
出産の際に安産を願い妊婦の枕元にも掲げられたらしい。
利根川下流流域地帯から房総半島中部にかけての信仰の広がりには、
この版木が原本として大きく寄与していると考えられるそうだ。
これまで出てきた待道大権現
これまで、
待道大権現が祀られていた場所ってどこがあっただろうか?
参考までに、
どうぞ。
というわけで…
新四国相馬霊場八十八ヶ所と、
周辺スポットポタリング。
今回は、
22番札所の岡発戸白泉寺とお隣の岡発戸八幡神社の敷地にある待道社でした。
利根川流域の下総地域に見られる安産祈願の女人講である待道講、
ここがその発祥の地だったとは。
こういう発見があると、
やはりあちこち周りたくなるものなのだ。


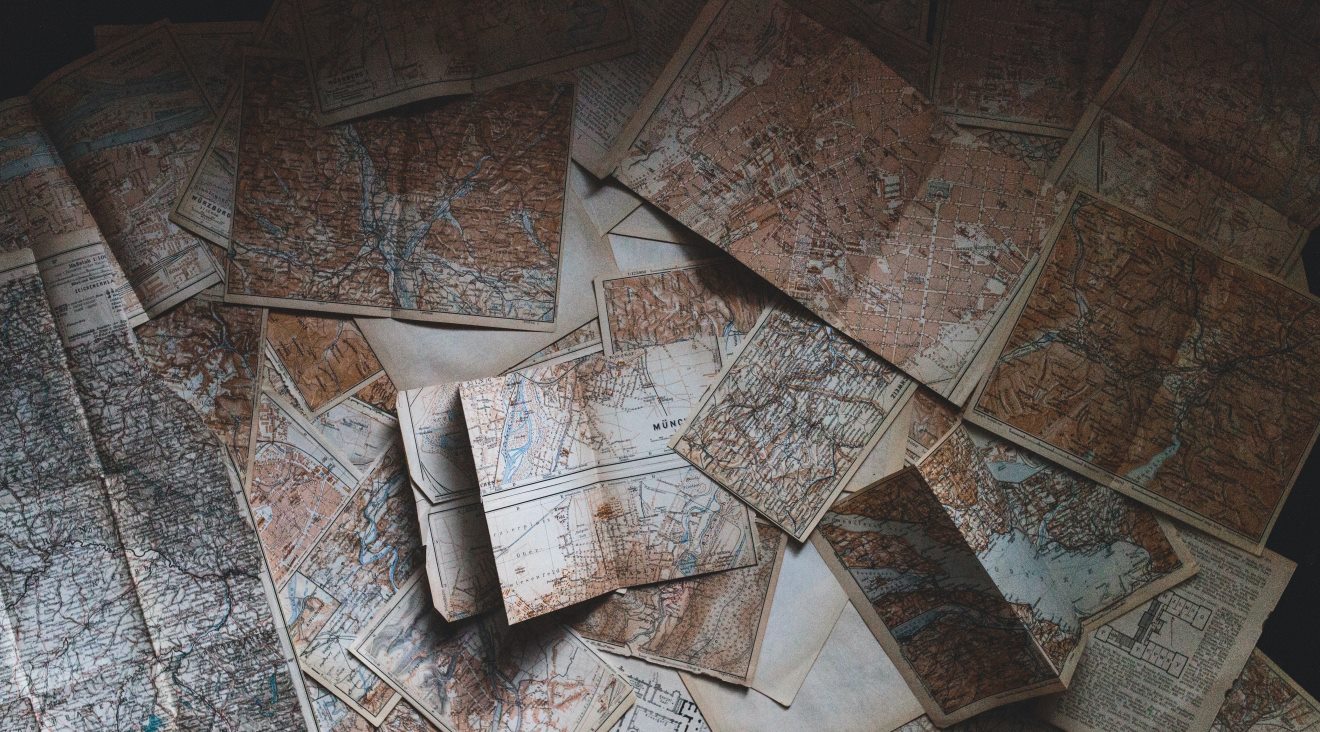



コメント