
さて、
東葛印旛大師88ポタリング。
ここまで訪れた地区は、
こんな感じ。
今のところ全て旧沼南地域17地区で、
そのうちの7地区。
札所27・元札所4・掛所6、
となる。
・手賀地区
札所6・掛所2
・布瀬地区
札所4・元札所1
・箕輪地区
札所4・元札所1
・片山地区
札所1
・鷲野谷地区(含染井入新田地区)
札所6・元札所1
・泉地区
札所4・掛所3
・柳戸地区
札所2・掛所1・元札所1
それで今回は、
旧沼南地域の17地区の内の8地区目になる岩井地区。
ここは、
鷲野谷地区と箕輪地区の間になる。
地図だと、
こんな感じ。
岩井地区は、
平将門スポットとして少し前に訪れているけど再訪問。
岩井地区
①勝矢堂 掛所
②龍光院 6・73番札所
※将門神社 元6番
先ずは掛所である、
勝矢堂から。
掛所 勝矢堂

将門通りを手賀沼とは逆側から入るところ、
岩井バス停前の一角にあるのが東葛印旛大師掛所の勝矢堂。

お堂の左手前には、
明治四十五年(1912年)の出羽三山・四國西國・秩父坂東供養塔。

左横には、
小さな五重石塔などなど。

右側には、
明治四十二年(1909年)の大師道と刻まれた標石などなど。

お堂の扁額は、
何て書かれているのか?

ただ、
勝矢堂ではない気がする。
岩井地区石塔群

将門通りを進んで左に曲がると、
道角に石塔が並んでいる。

奥の右にあるのが、
宝永2年(1705年)板碑型庚申塔。

真ん中が、
寛政五年(1793年)青面金剛尊塔。
左が、
文久二年(1862年)太子宮塔。

人差し指が上に彫られている明治四十二年(1909年)の大師道道標は、
七三番が辛うじて読めるので龍光院を指しているんだろう。

こちらも道標で、
片側には箕輪大井ヲ経テ柏ニ至ル。
もう片側には、
若白毛ニイタル。
将門神社

将門神社は、
東葛印旛大師第6・73番札所の龍光院の隣というか敷地内にあるのは以前紹介した通り。
東葛印旛大師第6番札所は、
文政期から昭和期までは将門神社にあったが龍光院に移されている。
とは言っても、
将門神社と龍光院のハッキリとした境は特にない。

岩井青年館の建物の軒下が、
将門神社の参道になっている。

この軒下を進むと階段があって、
その先に将門神社。

この本殿の彫刻は、
何度見ても素晴らしい。

社殿前には、
石造物が散在している。
例えば、
読めない石祠。

例えば、
手水舎前に横並びの2基の石燈籠。

参道を挟んで、
3基の石燈籠。

その手前の狛犬も、
結構時を経ている感じだ。

右端に写っている石祠は、
ちょっと読めず。

その隣は、
奉需廿三夜供養塔と読める。

他にも光明真言供養塔や子安観音塔、
四國西國霊場巡拝記念碑や丸彫りのお地蔵様などなど。

将門神社の右、
龍光院の本堂裏にも何やらある。

手前に手水鉢、
正面には台座に氏子安全と彫られた鹿嶋大神宮碑。

両脇には、
石祠。

その左にはお堂、
左手前には石灯篭。

まあいろいろあるんだけれど、
ここは今回初めて見た場所だ。
沼南の歴史をあるく21 将門神社・龍光院

さて、
東葛印旛大師第6・73番札所の龍光院。

創建は、
長享2年(1488年)と言われている。

山門の左には、
沼南の歴史をあるく21 将門神社・龍光院の白い標柱。

平将門を祭神とした珍しい神社で、
沼南の歴史をあるく21 将門神社・龍光院
本殿は安政六年(一八五九)の再建です。
隣接する龍光院は真言宗豊山派の寺院で、
境内の地蔵堂には如蔵尼が将門とその一族を弔ってまつったという地蔵尊

そして、
第73番の大きな標石。
本堂は、
文化十二年(1815年)の再改築。

ここにも、
お寺の名前が書かれた絵で描かれた小坊主の看板があった。

これまでも、
何回か見た気がするが四国八十八カ所にも同じようなものがあるらしい。
龍光院地蔵堂

敷地内には、
如蔵尼が将門とその一族を弔ってまつったという地蔵尊がある地蔵堂がある。

地蔵堂左手前には、
文政十三年(1830年)の六地蔵六面石幢。

地蔵堂手前右には、
手水鉢やら常夜燈。

更に、
お地蔵様など。

ここには、
何回か出てきた柏のむかしばなしの⑤地獄から戻ったお姫さまの標石がある。

これにもQRコードが付いているので、
動画を観ることができる。
沼南の歴史をあるく23 岩井庚申塔群

この安政三年(1856年)の再建の地蔵堂の脇には、
沼南の歴史をあるく23岩井庚申塔群の白い標柱がある。

この場所は岩井地区と箕輪地区の境にあたります。
沼南の歴史をあるく23 岩井庚申塔群
庚申塔は九基あり、
大部分は塚の上に造立されており、
正徳年間から明治初期にかけてのものです。
この場所は、
はどう考えてもここではない。
多分開発によって、
ここにお引越ししてきたのだろう。
庚申塔ではないが、
弘化四年(1847年)山神まで読める石碑と矢印のある道標。
正面は、
若白毛風早と読める。
左側面は、
大井ヲヘテ柏流山。

標柱にあった九基の庚申塔は、
もっと増えていてこんな感じ。
左が宝暦四年(1754年)の青面金剛尊塔、
右が正徳二年(1712年)の二童子付の青面金剛像塔。

右の青面金剛は、
ショケラに見えない何かを持っている。

欠けたのかもしれないけど、
ショケラっぽくない。

そして青面金剛王塔が、
3基続く。

そして、
文字庚申塔。

更に、
青面金剛王塔。

全部で、
5基が並ぶ。

これらの列の前にも、
なんだか色々。
お猿、
なんだろうか?

丸彫りの、
小さなお地蔵様。

これは、
読めず。

といった具合で、
なかなかヴァラエティに富んだ感じで面白い。
東葛印旛大師第6番

この龍光院敷地にある東葛印旛大師札所の1つは、
第6番で将門神社の近くにある。

六番しか残っていない標石が、
お堂の横にある。

さて実際の四国八十八所霊場の第6番は、
大師堂前から湧き出る宿坊の温泉とラジウム鉱泉入りの薬湯が有名な安楽寺。
所在地:徳島県板野郡上板町
創建年:(伝)弘仁6年(815年)
開基:(伝)空海(弘法大師)
山号:温泉山
院号:瑠璃光院
寺号:安楽寺
宗派:高野山真言宗
本尊:薬師如来
真言:おん ころころ せんだりまとうぎ そわか
御詠歌:かりの世に 知行争う むやくなり 安楽国の 守護をのぞめよ
東葛印旛大師第73番

東葛印旛大師第73番は、
観音堂の手前にある。

実際の四国八十八所霊場の第73番は、
弘法大師7歳の時に一生成仏が約束された地である出釈迦寺。
所在地:香川県善通寺市
開基:(伝)空海(弘法大師)
山号:我拝師山
院号:求聞持院
寺号:出釈迦寺
宗派:真言宗御室派
本尊:釈迦如来
真言:のうまく さんまんだ ぼだなん ばく
御詠歌:迷いぬる 六道衆生 すくわんと 尊き山に 出づる釈迦寺
というわけで…
今回の東葛印旛大師88ポタリングは、
岩井地区第6・73番。
その第6・73番がある、
龍光院。
そして、
掛所の勝矢堂。
更に、
以前にも1度出てきた同じ敷地内にある将門神社。
沼南の歴史をあるく23岩井庚申塔群や、
如蔵尼が将門とその一族を弔ってまつったという地蔵尊がある地蔵堂など。
東葛印旛大師第6・73番ポタリングMAP
過去分1はこちら


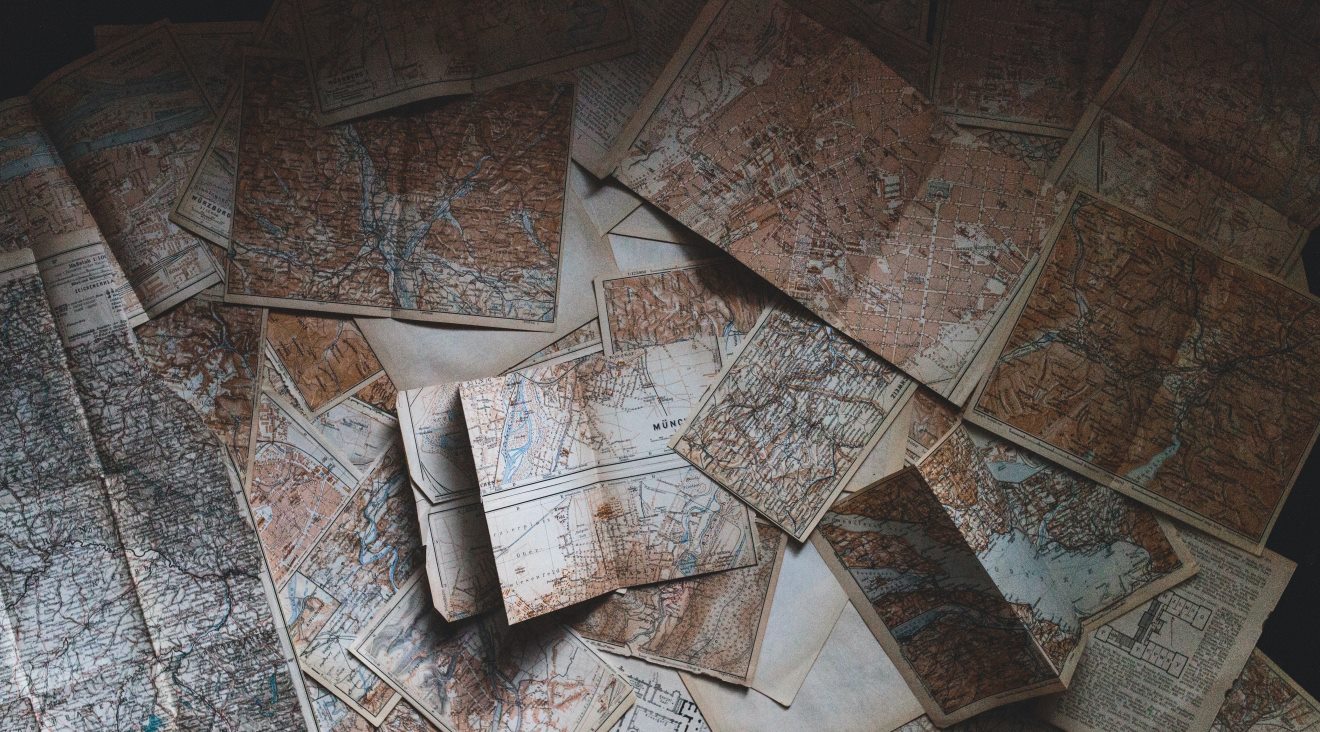


コメント